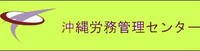2009年06月20日
デフアート

ふと、NHK教育のテレビで、「みんなの手話」という番組を見ていると、「デフアート」について、紹介されていました。
デフアートの「デフ」(=deaf)とは、“耳が聴こえない”という意味で、耳が聴こえない人の世界を芸術の上で表現されているもののことだそうです。
私は、初めて、知りました。
言われてみれば、耳の聴こえない人の独自の世界があるのは当然です。
耳が聴こえる生活と聴こえない生活は、どうしても同じ世界ではないと思います。
もちろん、必要以上に「違い」を強調するつもりはありませんが・・・。
ともかく、違いがあることは紛れもない事実です。
異質性は、コミュニケーションの世界に顕著に表れます。
今でこそ、「手話」は、市民権を獲得しているようにも見えますが、それは、日本ではほんの10年~20年程度のことであって、それ以前は、ろう学校ですら、手話教育を思うようにできなかった時代があると言われます。
実際に、私の両親は、私が高校生の頃(15年~20年位前)までは、自由に手話を使うことすらためらわれるような環境に置かれてきました。
耳の聴こえない人の方が、コミュニケーションのうえでは、我慢に我慢を重ねて生きていかなければならない環境であったといえます。
口話(こうわ=口の動きを読み取るやり方)での会話を余儀なくされ、相手の話していることがさっぱりわからない、自分の伝えたいことも全く伝わらない・・・そんなストレスだらけの世界です。
私の両親と同じような経験をされている方が、フランス留学を契機に手話のすばらしさを伝えようと、絵本を作り、出版されているそうです。
タイトルは、「手話で生きたい (デフアート絵本) (単行本) 」
作者は、乘富 秀人(ノリトミ ヒデト)さんという方だそうです。
なお、6月21日19:00~19:25からNHK教育にて放送される「みんなの手話」でも紹介されるそうです。 (再放送 : 6月27日 11:15~11:40)
お時間のある方は、ぜひともご覧下さい。
話は変わりますが、手話にも地域性があるとも聞きますが、口で話す言語よりも国際的に共有しやすいような言語であるような気もします。
手話の言い回しには、助詞などがなく、英語やフランス語にも近い世界のような気もするので、手話によって国境の壁が超えられるといいなあなんて思ってしまいます。
世界共通の言語なんて、実現できたらすごいことですよね。
夢のような世界かもしれませんが・・・。
ジョン・レノンの「イマジン」の世界かもしれません。
Posted by coda at 22:22│Comments(0)
│コーダ関連