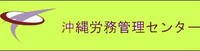2008年12月31日
社会不安障害(SAD)
今日の沖縄タイムス朝刊の記事の中に、「社会不安障害(SAD)」についての記事がありました。
私も、大変思い当たるふしがありました。
社会不安障害(SAD)とは、人前での話などに強い苦痛を感じたり、ドキドキしたりして、身体症状などが出たり、日常生活にも支障をきたす症状のことを指すそうです。
わかりやすく言えば、重度の「あがり症」ということになるようです。
私も、思い返せば、この症状に当てはまっていたかもしれません。
私の場合は、小学校の3年くらいに、全校生徒の前で、自分の生い立ちについて発表する機会があり、体が震えてしまって、まったくうまくしゃべれなかったことが思い出され、それ以降、人前で話すのが特に苦手になっていったように思います。
この経験が、今思えば引きこもりの原体験だったかもしれません。
人の目が怖くて仕方なくなってしまったのです。
社会不安障害の患者が恐怖を感じる場面の例として、以下の場面があげられるそうです。
1.大勢の前で話すとき
2.公式な席であいさつするとき
3.集会で自己紹介するとき
4.会議で指名され意見を言うとき
5.権威ある人と話をするとき
6.よく知らない人に電話するとき
7.初対面の人と話をするとき
8.面接を受けるとき
9.人に見られながらサインするとき
10.外で食事するとき
以上のどれもが、社会生活、特に社会人になると、多かれ少なかれ求められるものです。
このような状況でうまく対処できない人が少なからず存在するということです。
この、社会不安障害による年間労働損失額は、20歳から60歳の患者に限って見ても約1兆5000億円にものぼるとみられるそうです。
私は、個人的には、「話下手やあがり症で何が悪い!!」と思っています。
いってみれば、“開き直り”なのですが・・・。
確かに、コミュニケーションは必要なことです。
しかし、話下手や、あがり症というのは、人のほんの一面の性質でしかありません。
社会不安障害には、薬を使った治療と認知行動療法という方法を用いて治療が行われるそうです。
治療により、かなり改善される症状であるとのこと。
私自身も、この症状については、名前程度しか知りませんでした。
米国では、この患者が7~8人に1人とも言われるそうで、日本でもかなり増加しているとのことです。
それだけ、社会が寛容でないことの証しなのかもしれません。
こうした症状の改善には、何より社会的認知の拡大が必要であると思われます。
私も、大変思い当たるふしがありました。
社会不安障害(SAD)とは、人前での話などに強い苦痛を感じたり、ドキドキしたりして、身体症状などが出たり、日常生活にも支障をきたす症状のことを指すそうです。
わかりやすく言えば、重度の「あがり症」ということになるようです。
私も、思い返せば、この症状に当てはまっていたかもしれません。
私の場合は、小学校の3年くらいに、全校生徒の前で、自分の生い立ちについて発表する機会があり、体が震えてしまって、まったくうまくしゃべれなかったことが思い出され、それ以降、人前で話すのが特に苦手になっていったように思います。
この経験が、今思えば引きこもりの原体験だったかもしれません。
人の目が怖くて仕方なくなってしまったのです。
社会不安障害の患者が恐怖を感じる場面の例として、以下の場面があげられるそうです。
1.大勢の前で話すとき
2.公式な席であいさつするとき
3.集会で自己紹介するとき
4.会議で指名され意見を言うとき
5.権威ある人と話をするとき
6.よく知らない人に電話するとき
7.初対面の人と話をするとき
8.面接を受けるとき
9.人に見られながらサインするとき
10.外で食事するとき
以上のどれもが、社会生活、特に社会人になると、多かれ少なかれ求められるものです。
このような状況でうまく対処できない人が少なからず存在するということです。
この、社会不安障害による年間労働損失額は、20歳から60歳の患者に限って見ても約1兆5000億円にものぼるとみられるそうです。
私は、個人的には、「話下手やあがり症で何が悪い!!」と思っています。
いってみれば、“開き直り”なのですが・・・。
確かに、コミュニケーションは必要なことです。
しかし、話下手や、あがり症というのは、人のほんの一面の性質でしかありません。
社会不安障害には、薬を使った治療と認知行動療法という方法を用いて治療が行われるそうです。
治療により、かなり改善される症状であるとのこと。
私自身も、この症状については、名前程度しか知りませんでした。
米国では、この患者が7~8人に1人とも言われるそうで、日本でもかなり増加しているとのことです。
それだけ、社会が寛容でないことの証しなのかもしれません。
こうした症状の改善には、何より社会的認知の拡大が必要であると思われます。
Posted by coda at 14:09│Comments(0)
│メンタルヘルス