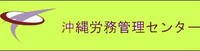2009年01月21日
障がい者関連の助成金2~障害者作業施設設置等助成金

今回は、障がい者関連の助成金のうち、「障害者作業施設設置等助成金」と「障害者福祉施設設置等助成金」について簡単に触れたいと思います。
なぜ、この助成金について触れようと思ったかといいますと、この助成金が、福祉での起業を想定されているという点もありますが、私自身の過去の経歴も、この助成金と大きく関係があるからです。
実は私は、約10年前は、とある福祉施設(精神障がい者向けの作業所)の事務担当をしておりました。
現在は、3障害(身体、知的、精神)を統合する形での国の施策があるようですから、精神障がい者に限定していないかとも思われますが、当時は、「精神障がい者小規模作業所」と呼ばれる施設でした。
この施設は、当時の所長(女性看護師)が、精神障がい者の地域の受け皿を作りたいという理想のもと、まったくのゼロから私財を投げ打って築き上げたものでした。
私が、事務職として携わるようになったのは、設立後数年したときだったかと思います。
当時、まだまだ、行政の間ですら、精神障がいへの取り組みは、他の障がい(身体、知的)と比べてもかなりの遅れを取っていましたので、行政関係者とのやりとりも一筋縄ではいかないものがありました。
当時の、施設運営費は年間たったの330万円!!
この、330万円で、施設の家賃や水光熱費、人件費などをほとんどまかなわないといけなかったのです。
家賃と水光熱費だけで、月10万円余、年間120万円以上にはなりました。
それに対し、必要な人員は最低でも4~5人。
とても人件費がまかなえる状態ではありませんでした。
設立者でもある所長はもちろん、ボランティア。
私は月10万円、その他のスタッフも、月わずかばかりの手当(数万円程度)しか渡せない状態でした。
私自身、他のスタッフに、毎月のわずかばかりの手当を手渡すのは、かなり心が重かったのを今でも覚えています。
もちろん、雇用保険や社会保険に入る余地などありません。
そのため、資金調達は、事務職の私にとっても頭痛の種でした。
そこで、当時、ほとんど知識もなかった私が思いついたのが、助成金の情報集めでした。
なかなか成功はしませんでしたが、応募できそうなものは、書類を作成して、応募していました。
その後、この施設ではNPO法人を立ち上げ、現在は、就労支援に力を入れた活動を積極的にしているようです。
私は、NPO法人を立ち上げる部分まで関わっておりました。
このような経歴もあり、この、「障害者作業施設設置等助成金」「障害者福祉施設設置等助成金」の名称を見ると、当時のことが思いだされます。
「当時、このような助成金があったなら・・・、あったとして、知っていたら・・・」などと思うわけです。
高い理想を掲げて、献身的に活動しても、やはり、運営資金がないと行き詰まってしまう、そんな厳しい現実があることを私は痛感したのです。
話を、助成金に戻します。
ただし、「障害者作業施設設置等助成金」「障害者福祉施設設置等助成金」は、いわゆる社会福祉施設向けの助成金ではありません。一般に社会福祉施設というと、社会福祉法に定められている施設、例えば、身体障害者授産施設などを指すのですが、この施設では、日常の作業やリハビリを通じて、心身の維持・回復を目指し、ここでの作業を行う人は、「利用者」と呼ばれます。作業を行う利用者に対して、「工賃」と呼ばれるものが支給される場合もありますが、これは、一般の労働に適用される最低賃金は適用されていません。
それに対し、ここでいう助成金の「施設」とは、労働者として雇い入れることを前提としています。つまり、しっかりと最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
条件は、以下のようになっています。
【障害者作業施設設置等助成金の条件】
1.支給対象者となる障がい者を新規または継続して雇い入れること
・身体障がい者(短時間労働者を除く。) ・重度身体障がい者である短時間労働者
・知的障がい者(短時間労働者を除く。) ・重度知的障がい者である短時間労働者
・精神障がい者(短時間労働者を含む。)
・上記の障がい者である在宅勤務者
2.支給対象障害者の作業を容易にするために配慮された施設又は設備(「作業施設等」)の設置・整備を行う事業所の事業主
3.作業施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇用の継続が困難な事業所の事業主
詳しくは、こちらをご覧ください。
【障害者福祉施設設置等助成金の条件】
この助成金名称は、少し誤解を招きやすいです。わかりやすくいうと、「福利厚生のための設備・施設を充実させるための助成金」ということが言えると思います。例えば、従業員のための専用休憩室を設置するような場合に、助成金をもらえるといったことになるでしょうか。
1.支給対象者となる障がい者を新規または継続して雇い入れること
・身体障がい者(短時間労働者を除く。) ・重度身体障がい者である短時間労働者
・知的障がい者(短時間労働者を除く。) ・重度知的障がい者である短時間労働者
・精神障がい者(短時間労働者を含む。)
・上記の障がい者である在宅勤務者
2.支給対象障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備(賃借による設置を除く。)を行う事業主等
3.認定申請日以前1年間に、障害者を事業主等の都合により解雇しておらず、障害者の雇用の安定について努力していると認められる事業主等(事業主団体の場合は、構成事業主すべてがこの要件を満たしている必要があります。)
4.福祉施設等の設置又は整備を行うことにより支給対象障害者の福祉の増進を図ることが適当であると認められる事業主等
詳しくは、こちらをご覧ください。
ポイントとしては、「障害者作業施設設置等助成金」の方は、賃貸による作業施設の整備も認められているという点です。
「第1種」と「第2種」に分かれており、前者が自前で整備する場合、後者が賃貸で整備する場合となっております。
一方、「障害者福祉施設設置等助成金」の方は、「賃貸」が認められていません。なぜ、このようになっているのかは不明ではありますが・・・。
また、さらに重要な点として、どちらも、事前に着手してはいけないという点です。
助成金を申請して認定がおりてから作業施設、福祉施設(福利厚生のための施設)を設置しないと、助成金はおりないということです。
もし、障がい者の社会復帰を目指すための本格的な施設を作りたい際には、ぜひとも検討したい助成金であると思われます。

Posted by coda at 15:55│Comments(4)
│助成金(厚生労働省)
この記事へのコメント
codaさんのご苦労が目に浮かぶようです。
ボク自身、今現在も奈良県内にあるNPOに関わっていますが、活動費はいつも不足しています。障害者福祉の関係ではないのですが、人権や環境の問題に取り組んでいるNPOです。
今は、派遣切りの問題を環境問題とリンクさせて、何かできないかと考えたりしています。オバマ大統領の「グリーンニューディール」みたいに…、っていったら大ボラになりますね(笑)
ボク自身、今現在も奈良県内にあるNPOに関わっていますが、活動費はいつも不足しています。障害者福祉の関係ではないのですが、人権や環境の問題に取り組んでいるNPOです。
今は、派遣切りの問題を環境問題とリンクさせて、何かできないかと考えたりしています。オバマ大統領の「グリーンニューディール」みたいに…、っていったら大ボラになりますね(笑)
Posted by okuuda at 2009年01月21日 21:39
okuudaさん、お返事遅くなってごめんなさい。
okuudaさんも、NPOに関わっているのですね。
なかなか大変なこととお察しします。
障害者関連で言いますと、言葉は悪いかもしれませんが、助成金や資金集めをしやすいのは、就労支援、つまり、障害者の雇用ということになるようですね。
でも、個人的には、果たして、それでいいのか・・・とも思ったりします。
もちろん、働くことは大事なことですが、あまりに強調されると、今度は、障がいを持つ多くの人々の「行き場」がなくなってしまう、そんな気がしてなりません。
福祉と労働の両立ってなかなか難しいのでしょうか・・・?
なかなか答えの出ることではありませんが、そんなことを考えたりします。
okuudaさんも、NPOに関わっているのですね。
なかなか大変なこととお察しします。
障害者関連で言いますと、言葉は悪いかもしれませんが、助成金や資金集めをしやすいのは、就労支援、つまり、障害者の雇用ということになるようですね。
でも、個人的には、果たして、それでいいのか・・・とも思ったりします。
もちろん、働くことは大事なことですが、あまりに強調されると、今度は、障がいを持つ多くの人々の「行き場」がなくなってしまう、そんな気がしてなりません。
福祉と労働の両立ってなかなか難しいのでしょうか・・・?
なかなか答えの出ることではありませんが、そんなことを考えたりします。
Posted by coda at 2009年01月22日 20:17
at 2009年01月22日 20:17
 at 2009年01月22日 20:17
at 2009年01月22日 20:17ボクも同じことを思っています。
「障害者自立支援法」も「自立支援」と言いながら結局「障害者も甘えずに働け!」と言っているような気がしてなりません。
障害は千差万別。誰一人として否定されるべきではない、はずなんでが…。
「障害者自立支援法」も「自立支援」と言いながら結局「障害者も甘えずに働け!」と言っているような気がしてなりません。
障害は千差万別。誰一人として否定されるべきではない、はずなんでが…。
Posted by okuuda at 2009年01月22日 22:58
okuudaさん、ありがとうございます。
障害者自立支援法については、私は詳しくはわからないのですが、以前、私は、重度の障がいを持つ人の在宅生活の支援に個人的に関わっていたこともあるのですが、こうした、重度に障がいを持つ人は、どうしても、24時間体制に近い形のケアが必要となりますから、それに伴い、負担が大きくなりますよね。応益負担の考え方で行くと・・・。
私が関わっていたときはまだ、自立支援法が施行される前でしたが、その時ですら、じゅうぶんなケアが行き届かず、ボランティアを頼りにせざるを得ない状況がありました。
そのときと比べてすら、現在は、良くなっているとはとても思えません。
どちらかというと悪くなっているようにも思われます。負担が重くなる方向にありますから。
障害者自立支援法が、逆に「自立」を阻害するような現状があるんですよね。
障害者自立支援法については、私は詳しくはわからないのですが、以前、私は、重度の障がいを持つ人の在宅生活の支援に個人的に関わっていたこともあるのですが、こうした、重度に障がいを持つ人は、どうしても、24時間体制に近い形のケアが必要となりますから、それに伴い、負担が大きくなりますよね。応益負担の考え方で行くと・・・。
私が関わっていたときはまだ、自立支援法が施行される前でしたが、その時ですら、じゅうぶんなケアが行き届かず、ボランティアを頼りにせざるを得ない状況がありました。
そのときと比べてすら、現在は、良くなっているとはとても思えません。
どちらかというと悪くなっているようにも思われます。負担が重くなる方向にありますから。
障害者自立支援法が、逆に「自立」を阻害するような現状があるんですよね。
Posted by coda at 2009年01月23日 19:38
at 2009年01月23日 19:38
 at 2009年01月23日 19:38
at 2009年01月23日 19:38