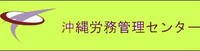2008年11月20日
賞味期限切れ商品販売問題について
本日(11月20日)付けの沖縄タイムス朝刊1面トップに、金秀商事による賞味期限切れ商品の販売問題について取り上げられました。
私も、県内の某王手流通業の商品管理の業務に4年半以上関わったこともあり、思うところがありますので、現場担当の立場からこの問題について述べたいと思います。
金秀商事は、みなさんご存知の方も多いでしょうが、低価格の商品戦略で有名です。
低価格を実現するためには、流通コストを抑えていかなければなりません。当然ながら、人件費に関してもです。
私自身、入荷や在庫管理といった商品管理の業務に携わっていたので、わかるのですが、商品管理を徹底させようとすると、どうしても人件費は増える傾向が出てきます。
在庫管理ソフト等のIT技術を駆使すれば、人件費を削れそうに思われるかもしれません。しかし、現実のところ、現場レベルまでは、さほどIT化は浸透していません。
なぜなら、IT化には、大きな導入コストもかかりますし、運用には、従業員の教育システムも必要です。企業にとっては、二の足を踏む状況があります。
それでも、入荷に関しては、ある程度機械化は進んでいるようです。しかし、在庫管理については、特に食品に関しては、賞味期限の管理が複雑になるため、現場担当者の「目」が頼りになります。
ところで、みなさんは、スーパーの商品、たとえば、牛乳を後ろの列から取ったりしませんか?
やはり、新しいもの、長持ちする商品を選ぶことは多いのではないでしょうか。
この行為は、消費者としては当然の行為かもしれません。
しかしながら、販売する側の担当者から見ると、その行為により、賞味期限の管理が複雑になってきます。同じ牛乳という商品でありながら、賞味期限が何通りも存在することになるのですから。
人件費が極度に切り詰められた現場では、こうした複雑な在庫管理に対応しきれなくなってしまうのです。
かといって、金秀商事のように、賞味期限切れ商品の販売は許される問題ではありません。
ただ、今回の問題により、行き過ぎたコスト削減は、生命を脅かしかねない、ということを示しました。消費者としても、価格のみではなく、総合的に商品を判断する必要が出てきていると言えそうです。
私も、県内の某王手流通業の商品管理の業務に4年半以上関わったこともあり、思うところがありますので、現場担当の立場からこの問題について述べたいと思います。
金秀商事は、みなさんご存知の方も多いでしょうが、低価格の商品戦略で有名です。
低価格を実現するためには、流通コストを抑えていかなければなりません。当然ながら、人件費に関してもです。
私自身、入荷や在庫管理といった商品管理の業務に携わっていたので、わかるのですが、商品管理を徹底させようとすると、どうしても人件費は増える傾向が出てきます。
在庫管理ソフト等のIT技術を駆使すれば、人件費を削れそうに思われるかもしれません。しかし、現実のところ、現場レベルまでは、さほどIT化は浸透していません。
なぜなら、IT化には、大きな導入コストもかかりますし、運用には、従業員の教育システムも必要です。企業にとっては、二の足を踏む状況があります。
それでも、入荷に関しては、ある程度機械化は進んでいるようです。しかし、在庫管理については、特に食品に関しては、賞味期限の管理が複雑になるため、現場担当者の「目」が頼りになります。
ところで、みなさんは、スーパーの商品、たとえば、牛乳を後ろの列から取ったりしませんか?
やはり、新しいもの、長持ちする商品を選ぶことは多いのではないでしょうか。
この行為は、消費者としては当然の行為かもしれません。
しかしながら、販売する側の担当者から見ると、その行為により、賞味期限の管理が複雑になってきます。同じ牛乳という商品でありながら、賞味期限が何通りも存在することになるのですから。
人件費が極度に切り詰められた現場では、こうした複雑な在庫管理に対応しきれなくなってしまうのです。
かといって、金秀商事のように、賞味期限切れ商品の販売は許される問題ではありません。
ただ、今回の問題により、行き過ぎたコスト削減は、生命を脅かしかねない、ということを示しました。消費者としても、価格のみではなく、総合的に商品を判断する必要が出てきていると言えそうです。
Posted by coda at 19:00│Comments(0)
│経営